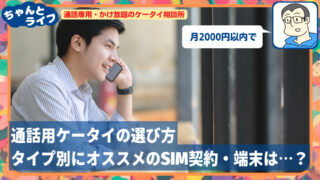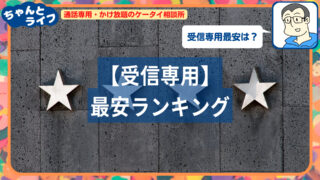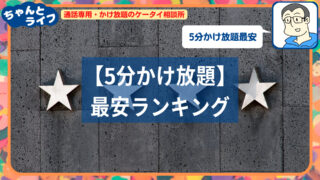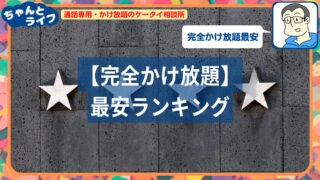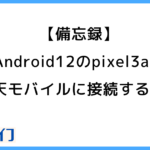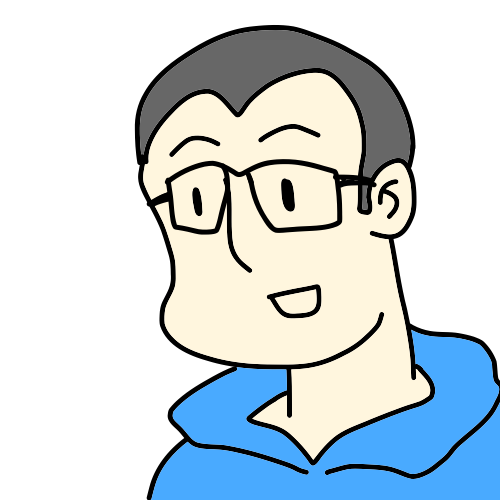
「iPhoneが値上がりして困っちゃうよ!」
という声が最近増えてますが、円高の影響もあってスマホ含め物価全体が上がってますよね。
それでも8割の人は1年おきに最新のiPhoneを買えるのに、そのチャンスを放置してます。
1年おきにiPhoneの最新機種を買える可能性があるのに、気づいてない人ってどんな人?
結論から言うと、ドコモ、au、ソフトバンクといった大手携帯電話会社(3大キャリアと呼ばれています)を使っている人が当てはまります。
3大キャリア+楽天モバイルのユーザーの月々のケータイ代の平均は5146円です。
(調査によっては8000円を超えるというデータもあります。)
また、3大キャリア+楽天モバイルのユーザーは、携帯電話利用者の8割以上となっています。
この人たちは月1000円の格安SIMに切り替えることで、2年で9万6千円の節約ができる計算です。

でも”格安SIM”ってきいたことあるけど、よくわからないから不安!
という人もいると思いますが、節約したい人はとにかく行動してください。
切り替えないと大損します。
私は2014年にMNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ:電話番号を変えずに携帯電話会社を変更できる制度)で格安SIMに切り替えました。
結果、2023年までの9年間でトータル100万円以上の節約に成功しました。
平均して毎年12万円以上も節約している計算になります。
しかも、今は始めた頃よりもっと安いプランにしているので毎年約18万円ペースで節約が続いています。
この記事では、あなたが格安SIMに乗り換えることで節約できる金額と、格安SIMに乗り換える方法、オススメの格安SIMを紹介します。
この記事を読んで行動すれば、簡単に毎年数万円のお金を手元に残すことができるようになります!
そもそも格安SIMとは?

そもそも、格安SIMってなに?
という方もいると思うので、簡単に説明します。
携帯電話サービスを提供している会社には、MNOとMVNOがあります。
| MNO | 自前で基地局などの通信網を持っている会社 ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルなど |
| MVNO | MNOから通信網を間借りして携帯電話サービスを提供する会社 ビーモバイル、IIJmio、OCNモバイルONE、UQモバイル、ワイモバイル、LINEMO、マイネオなど |
このMVNOが提供している携帯電話サービスが一般的に「格安SIM」と言われています。
「格安」の理由は、MVNOは自前の通信網が無いのでお金がかかる設備投資が不要であること、オンライン契約が主なので販売店などのコストがかからないことがあげられます。
「SIM」とは、SIMカードという加入者を特定するためのID番号が記録されたICカードのことです。
スマートフォンはSIMカードを挿すことで通話やデータ通信ができるようになります。(最近は物理的なカードではなく、スマートフォンに搭載されているeSIMというものもあります。)
3大キャリアではショップ店員が設定の面倒を見てくれるので、SIMカードを見たことがないという人も多いかもしれません。
SIMカードは携帯電話会社ごとに発行するものなので、携帯電話会社を乗り換えた場合、スマートフォンから古いSIMカードを取り出し、新しいSIMカードに入れ替えます。
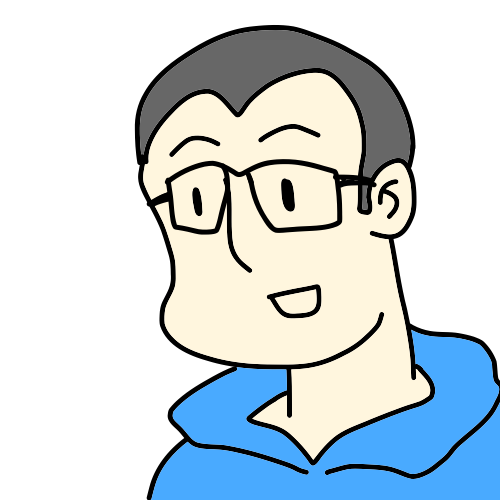
つまり「格安SIM」とは、「利用料金が格安な携帯電話会社のSIMカード」という意味ですが、「安い通信サービス」くらいでおぼえておけばOKです。
格安SIMでいくら節約できる?
まずは、格安SIMに切り替えることでどれくらい節約できるか計算してみましょう。
今回は例として月1000円の格安SIMに切り替えることとします。
携帯電話会社を切り替える手間に見合った金額になるでしょうか?
どうでしょうか?
乗り換える手間に見合った額になるでしょうか?
しかも、今切り替えると、今年だけじゃなく、来年も再来年も毎年同じ額の節約ができます。
ちなみに私は仕事の都合で2台持ちだったので、2013年までは毎月1万1000円かかっていました。
しかし、2014年に1台を格安SIMに替えたところ、月7300円に下がりました!
さらに、2016年にもう1台も格安SIMに替えて月3900円に下がりました!
2018年には親の回線契約も引き受けたので3台になりましたが、その後もこまめにプランを見直して、今は3台分で月2600円になっています。
本来であれば、9年間で150万円以上払っていたはずです。
でも、格安SIMに替えた2014年からの9年間は47万1600円で済んでいます。
今は毎月1万4900円の差、1年で17万8800円の差です。
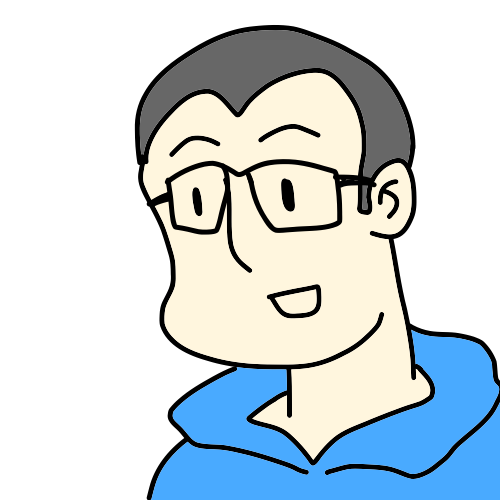
これだけの差額があれば、毎年最新のiPhoneに機種変できちゃいますよね!
格安SIMのデメリット(ただし解決策あり)
格安SIMは料金が安い分、デメリットもあります。
ここでは解決策と合わせて説明します。
キャリアメールが使えない→乗り換え後も使える!
ドコモなどの大手携帯電話会社では、「***@docomo.ne.jp」などのメールアドレス(「キャリアメール」と呼ばれています。)がついてきます。
格安SIMに乗り換えると、ドコモとの契約が切れるため、このメールアドレスも使えなくなってしまいます。 →キャリアを変えてもドコモメールが使い続けられる「ドコモメール持ち運び」サービスが月額330円(税込)で提供されています。(追記 2022年9月17日)
メールアドレスが変わると、二度とそのメールアドレスではメールの送受信ができなくなるというデメリットがあります。
ただ、これも考え方の転換で、「LINEがあるからいいや」と割り切るか、思い切ってフリーメールに切り替えるという方法です。
今はスマホ利用者の8割がLINEを使用しているそうです。
連絡を取るならLINEで十分と割り切れば、キャリアメールから解放されます。
また、フリーメールについては、グーグルが提供しているgmailならどの携帯電話会社でも使えるのでオススメです。
gmailなら今後も別の携帯電話会社に乗り換えたとしても使い続けられます。
それでも迷う人は、「330円で済むはずのメールアドレス代だけで毎月数千円、毎年数万円払い続けますか?」という話になってしまいますので、それぞれの価値観でお考え下さい。
実店舗が少なく初期設定を自分で行う必要がある
3大キャリアでは、実店舗に行くと手続きをしてくれる親切なスタッフがいて、手続きも親切にサポートしてくれて、すべて設定が終わったスマホを渡してくれます。
格安SIMは、基本的にすべて自分で設定する必要がありますので、ある程度の知識が必要です。
とはいうものの、だいたいのことは格安SIMのサイトを見ればわかりますし、検索すれば同じことで悩んだ人が書いた備忘録的な記事が見つかります。
「説明書を読んでもカラーボックスが組み立てられない」というレベルの人じゃないかぎり、手順どおりに進めれば問題なく設定ができるはずです。
また、最近は家電量販店に格安SIMの店舗が増えてますので、ここらへんのデメリットはどんどん小さくなっていると言えます。
通信速度が遅くなる時間帯がある
格安SIMでは、昼休みの時間帯や夕方などに通信速度が遅くなる場合があります。
これは都心など人口密度の高い地域でよく起こる現象です。
(私は地方に住んでいるのであまり感じたことはないです。)
ただ、これも対策がありまして、格安SIMの種類によってはそれほど遅くならないというものもあります。
それはいわゆる3大キャリアの「サブブランド」と呼ばれる格安SIMです。
具体的には、3大キャリアが自社やグループ会社で提供しているちょっと安めの携帯電話サービスです。
| メインブランド | サブブランド |
|---|---|
| ドコモ | ahamo
|
| au | UQ mobile |
| ソフトバンク |
自社やグループ会社のブランドということだけあって、ネットワーク帯域がしっかり割り当てられているようで、混みあって遅くなるということが比較的少ないです。
格安SIMへの切り替え手順
- スマホのSIMロック解除する
(2021年10月以降にスマホを購入した人や、すでにSIMロック解除済の人はスキップ) - フリーメールを作っておく(すでに持っている人やメール持ち運びする人はスキップ)
- 現在利用中の携帯電話会社からMNP予約番号を取る
- 乗り換え先の携帯電話会社に申し込む
- SIMカードが届いたらスマホに差し込む
- スマホにAPN設定を行い、通信可能になったことを確認する
基本的にすべてオンラインで手続きができますが、不安な場合は実店舗での手続きをオススメします。
オススメの格安SIMは?
オススメの格安SIMは、その人のタイプ別に異なります。
「自分はこのタイプだ!」というものがあれば、リンク先をのぞいてみてください。
- 毎月のデータ通信量が多かったり少なかったりする人
楽天モバイル
- ドコモの電波しか拾えない地域の人
OCNモバイルONE
- 家族でデータ通信量をシェアしたい人
OCNモバイルONE 、イオンモバイル
、イオンモバイル - LINEをよく使う人
LINEMO - Youtubeなどをよく使う人
BIGLOBEモバイル - 通話が多い人
HISモバイル、楽天モバイル
 、OCNモバイルONE
、OCNモバイルONE

- 実店舗で契約したい人
イオンモバイル、OCNモバイルONE 、UQ mobile
、UQ mobile、mineo
、HISモバイル
、楽天モバイル
 、LINEMO
、LINEMO
まとめ
ここまで読んでいただければ、格安SIMでかなりの額を節約できること、格安SIMに切り替えても使い勝手にそれほど影響がないことがお判りいただけたと思います。
もちろん格安SIMにはデメリットもありますが、デメリットの影響を軽減する方法もあります。
キャリアメールをやめてgmailやLINEを使うようにするなど、ちょっと習慣を変えるだけで格安SIMのデメリットはほとんど無くなります。
実店舗じゃなきゃ不安という方も、最近は実店舗が増えてきているのでほとんどデメリットは感じられません。
通信速度が遅くなるのが気になるという人も、3大キャリアのサブブランドなら比較的影響が少ないです。
格安SIMへの切り替え手順もインターネット上にたくさん情報があるのでそれほど困りません。
それでも不安な人は家電量販店に実店舗が増えているので、そちらで手続きすることで回避できます。
格安SIMはいろんな種類があるので、ライフスタイルや好みによって最適なものが選べます。
大事なことなのでもう一度言いますが、格安SIMでかなりの額を節約できます。
逆に考えると、格安SIMに切り替えないことでかなりの額を浪費しているとも言えます。
格安SIMに切り替えるかどうかで、毎年数万円の差が発生します。
私はこの9年間でトータル100万円、今では年18万円の節約ができています。
これを無視するかしないかはあなた次第です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。